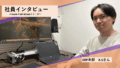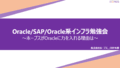今回はホープスで働く社員へ担当プロジェクトについてお話を伺いました!
今回お話を伺ったのは、ホープス在籍11年のH.W.さん。お客様先の社内DXを推進するプロジェクトにてリーダーを担当されています。
常にお客様と相対するH.W.さんの姿勢には、エンジニアとしてのキャリアアップに欠かせない心構えがありました。
【プロフィール】
H.W.さん (所属:アカウント本部 6グループ)
新卒でホープスに入社し8年ほど勤務。その後、新たな環境を求めて別の会社へ。
自身の苦手な分野も補い合え、チームで助け合いながら仕事ができるホープスの雰囲気が合っていると感じ、ホープスへ再入社。
現在は大手商社の情報システム部門にて、社内のDX推進のプロジェクトに従事。
―さっそくですが、まずは現在の業務内容について教えてください。
H.W.:現在はお客様先での社内DX推進プロジェクトを担当しています。主な業務は、お客様のアプリ開発の相談対応やデジタル人材の育成です。主にMicrosoftのPower Appsというローコード製品を用いて、非IT職の方々が自分たちでアプリを開発し、業務効率化を叶えていくことを支援しています。
―お客様のDX推進に携わっているんですね。
H.W.:そうですね、例えば、人事部、営業部、経理部などの各部署から、業務効率化のためのアプリ開発の相談を日々受けています。また、ガバナンスの運用も担当しています。非IT職の方々が作成したアプリでは、意図せずセキュリティ面の問題が発生することがあります。そのため、アプリを作成したい場合は申請を出し、こちらの部門の許可を得てから開発していただくというフローで運用しています。
―プロジェクトのチームはどのような構成でしょうか。
H.W.:デジタル部門には私とお客様側のプロパー社員がいて、全体で10人くらいのチームです。私はチームのまとめ役といった存在で、ホープスのメンバーではガバナンス対応や審査関係の担当、あとは生成AIの開発推進をやっていたりと、皆それぞれ役割は違いますが一つのチームとして動いています。単一のシステム開発チームではないので、かなり多様なメンバー構成だと思います。
―働き方はどのような感じでしょうか
H.W.:そうですね、1週間のうち3日はお客様先に出勤し、残り2日は在宅勤務といった感じですね。
お客様の相談対応が、どちらかというとオンラインよりは対面の対応が多いので、その頻度に合わせて出社しています。
―どういった流れでお客様からご相談をいただくのでしょうか?
H.W.:そうですね、MicrosoftのBookingsというサービスを使用していまして、そこからスケジュール予約を入れてもらいます。予約が入るとOutlookのスケジュールが自動で作成され、同時に会議室も予約されます。
―それは便利そうですね。相談の頻度はどのくらいですか?
H.W.:固定の相談枠が月・水・金にそれぞれ2時間ずつあり、週に6時間ですね。あとは細々とした相談を4、5件ほど追加でいただくので、合計で週に10時間程度でしょうか。
―ちなみに最近ではどのようなご相談がありましたか?
H.W.:先日は金属資源等を管理する部署の方から、原材料の在庫管理をExcelで行っており、時間と手間を短縮できないかという相談を受けました。結論として、MicrosoftのPower Appsを使ったアプリ開発の支援する方向で進めています。
―他にはどのような業務を担当されていますか?
H.W.:全体週40時間のうち、相談対応を除いた30時間は、チームのフォローや運営対応、進捗管理などに充てています。
チームメンバーから「お客様からこういう相談が来ているのですがどうしたらいいですか?」といった質問があるので、適宜フォローを行っています。
進捗管理については、メンバーが10人ほどいるので、毎週週報を作成しています。各メンバーのタスクと進捗、実績工数を集計し、週次で業務報告をお客様先に提出します。あとは、月次の請求もあるので、稼働実績を計算して金額を出すこともしています。PMのような役割に近い感じですね。
あとは市民開発(デジタル人材育成)の運営として計画の立案等、様々対応しています。
最近では、海外の関係会社へもシステム導入を進めたいという声が出ており、ヨーロッパや中国などの関係会社にいる現地のIT担当と打ち合わせを行い、ガバナンスの設定や運用方法など、仕組み化の対応をしています。
―ありがとうございます。一連の業務のなかで大切にしていることはなんでしょうか。
H.W.:そうですね、色々とありますが、ユーザーはどう思っているのかをよく考えるようにしています。結局はユーザーが納得できるかどうかが重要ですので、ユーザーの困っていることをしっかりと把握して解決することを意識しています。
例えば、保守費用が20万円かかるシステムを導入したいというお客様がいて、15万円なら予算が下りるということであれば、お客様側でもできる部分を切り出して、5万円分のコストカットを提案します。ユーザーの言うことをそのまま受けるのではなく、ユーザーがやりたいことをイメージし、最も良い形で実現できるように考えをめぐらせます。
―ユーザーと向き合うって大事ですよね。
ちなみにですが、直接ユーザーと関わらない形で開発していくことも多々あると思いますが、そういった際はどういったことを意識するのが良いでしょうか?
H.W.:そうですね、たとえユーザーと直接関わらなくても、やはりユーザーが何をしたいのかをイメージすることは大事です。設計上の指示だけでなく、この機能は本当にユーザーにとって使いやすいのだろうか、などと考えながら開発を進めていくべきだと思っています。
プログラマーとして設計通りに作るのは勿論正しいことですが、出来るかぎりユーザーが利用するシーンをイメージすることが大事です。テストの際にも、ユーザーの視点で動かすことで何かしらの気づきを得てほしいなと思っています。
これは若手エンジニアですとなかなか難しいことかもしれませんが、実際にユーザーと向き合って業務を進めるようになると、実感できると思います。
―優秀なSEを目指すにあたって、重要な心構えだと思います!
貴重なお話、ありがとうございました!

↑プライベートのH.W.さん とても楽しそうな旅行写真です。
株式会社ホープスでは一緒に働く仲間を募集しています!